2025/10/03
2025年9月27日(日)第391回グローバル・セッション・レポート 「英語という風に吹かれて」
開催後のレポート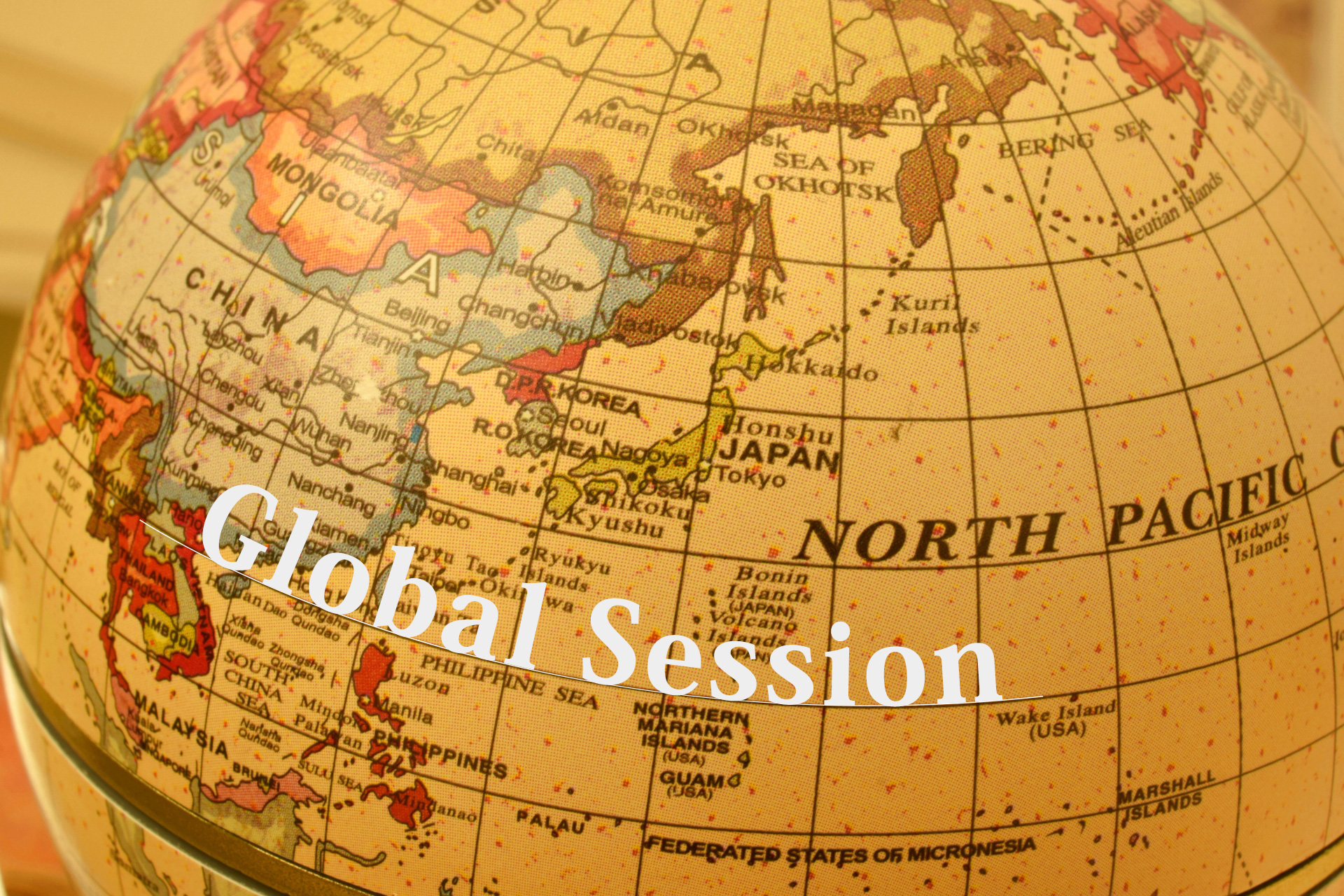
開催日:2025年9月27日(日)10:30~12:45
場所:ガレリア3階 会議室
ゲストスピーカー:畑佳延さん(元総合商社勤務)
コーディネーター:亀田博さん
参加者:9名
今回のタイトル:「英語という風に吹かれて」
内容:内容
- 英語との出会い
- 英語にどのように接し、学んで来たか
- 中学・高校時代
- 大学時代
- 社会人になって
- 英語を学んで良かったこと
- 英語について言いたいこと
- 今、していること
自己紹介
亀田(C)さん:畑さんは、GSでのプレゼンテーションは初めてですね。若い時から、ずっと英語と関わりを持って来られたのですね。では、自己紹介から始めましょう。
K・Tさん:個人で映画制作をしています。「Chair」という映画が今、少しずつ評判を得ていますが、英語との関わりも増えていますので、今日は、畑さんがどのように英語を学んで来られたのか興味があり参加しました。
N・Kさん:小学校の教員をしていました。退職後は、ひまわり教室と関わり、母語と日本語で大変な子どもたちが、二ヶ月もすると話す人がいることが驚きです。今は、ラジオ英会話講座と月に2度の英語教室で英語を取り戻そうと勉強しています。
Z・Yさん:GSでは、何度もお目にかかる人がいて、うれしいです。私は、外国につながる子どもたちの支援を学校でしています。子どもたちといっしょに勉強していきたいと思います。畑さんは、英語で新しい道を開かれたと思います。これから、子どもたちも多言語での新しい道をひらいてほしいと思っています。
M・Hさん:GSには、ちょこちょこ来ています。英語は、娘が以前、アメリカの大学に行くというので、もし、私がひとりでアメリカに行かねばならない時がきたらと、学び始め、飛行機の中の英語も理解できるくらいになりました。それ以後、外国に人を受け入れる時に、日本の食品を英語で説明するのに難儀しました。また、簡単な英語を話せるようにしたいと思います。
C・Yさん:中国から来て大阪に住んでいました。1年前に亀岡に来ていましたが、仕事の都合でまた、来月から大阪で仕事をすることになりました。パナソニックインダストリーの関係会社で、国際関係の部門を携わることと思います。11月からは、大阪から宇治へ通うことになります。今までの仕事でも英語、中国語、日本語など多言語を使っていました。日本語、英語、中国語が使えると言っても、仕事上、ニュアンスがそれぞれちがう場もあり、これからは、シンガポールとの関係もあるので、多言語を使いながら、もっと英語を学びたいと思っています。AIも使いながらですが。
N・Fさん:亀岡に生まれて、市役所に勤務しています。母が英語の先生でもあったので、小学校3年生から英語の学習を始めました。大学では国際関係学部だったので、もちろん英語での講座もあり、英語は必要でした。
児嶋:1999年から、亀岡交流活動センターで、Global Sessionを開始し、私が退職後は、オフィス・コン・ジュント主宰として継続し、今日は、391回目になります。毎回ゲストをお呼びし、レポートを書いて、150名くらいの会員にお送りしています。どの会もお話しも、セッションもおもしろいですね。
亀田さん:コーディネーターを最初から少ししてから続けています。大津市在住で、毎月1回か2回は亀岡に来ています。遠くないので京都から30分くらいで来れますね。この間、「国宝」の映画を外国人の友人と見に行きました。その人は5回目だそうですが。普通の日で、朝早いと高齢の方が後ろの指定席に多くいました。トイレに近いからかもしれませんが。映画を撮影した場所が、今は観光地になっているようです。旧琵琶湖ホテルなども。こんどの小泉八雲の映画もおもしろそうですね。
畑さん、ではお願いします。
グローバルセッション開始
畑さん:後期高齢者なので、プロジェクターなどを使わず、話しが飛んだり、繰り返してもご容赦ください。特別に研究したわけでもないので、よろしくお願いします。
- 英語との出会い
小学校からローマ字に興味を持ち、中学校へ行ったのが英語を好きになるきっかけでした。
- 英語にどのように接し、学んで来たか
◎中学・高校時代
①中学1年の英語教科書のLesson one: a pen, a bookとあり、単数形の表示があることを発見した。
②NHKラジオ・テレビの英会話番組(初級・中級)の聴講を始める
松本亨(ラジオ)・田崎清忠(テレビ初級:1年生の12月から)・
国弘正雄・村松増美(テレビ中級):インタビュー番組で時々のトピックスや文化的背景を学ぶ。(文化的背景を学ぶことにより、英語学習に深みが出た。)
*黙読だけではなく、声を出して朗読することにより、口が英語に慣れると同時に、耳に英語が自然に入ってくるので、一挙両得である。
③海外文通:同世代の若者と手紙で情報交換
テキストにPen pal募集の欄があり、試しに出すと、返事が来た。
筆記体の練習にもなった。
④訪日外国人との語らい:学習している英語会話を実践に移そうと、電車の中などで、観光客に話しかけた。快い返事が戻って来た。
⑤英語関連雑誌や本の購読
「時事英語研究」・「英語青年」・「Readers Digest」その他
⑥英文学を読む(精読・音読) Charles Dickens. Kazuo Ishiguroなど
⑦ワークキャンプに参加した。(日本基督教団主催)
アメリカの高校生とユースホステルに宿泊し、生活を共にしながら、近隣酪農農家の酪農地開拓作業を手伝う。(岩手県二戸郡)
一つの目的の下、共に勤労奉仕することで、強い絆が出来た。
◎大学時代
①実用英語技能検定試験(英検)1級に大学(同志社)1年に合格
特別の英検用の勉強はしていなかった。こつこつとやっていると、気づかないうちに成果が出た。
②ESSに入部:質を上げるためには、知識が必要とわかり、いろいろな活動をした。
Recitation Contest/ Speech Contest/ Debateなど
③海外青少年との交流~世界青少年交流協会での活動
1970年世界青少年交流協会主催の派遣団員募集に応募し、旧西ドイツを1か月訪問した。(ドイツ南部地方・ベルリン)
*ベルリンの壁を目の当たりにして、東西冷戦の厳しさを肌で感じた。
帰国後、海外からの青少年受け入れや交流事業を行う。(京都周辺の案内・会社訪問・意見交換会など)→交流活動は、すればするほど難しくなる。なぜなら、自国のことをよく知り、自分の意見を持っていなければならないから。
京都市・亀岡市とも協働
- 社会人
就職:海外との接点のある仕事を求めて、総合商社に入社
仕事の内容:主計・財務(経理)
米国会計基準に基づく英文の連結財務諸表の作成(Annual Report)
海外駐在(英国7年・米国5年)英国では発音の美しさに触れる。
- 英語を学んで良かったこと
- 世界に目を向けるきっかけになった。
- 世界との距離が近くなり、コミュニケーションの幅が広がった。
- 海外の情報に時々、直接触れることで視野が広がった。
世界の出来事、海外での報道の仕方、今 何が奉じられているかなど
- グローバルな人間関係を構築することができた。
ワークキャンプで知り合った米国人家族との交流
海外駐在で知り合った人々との絆(隣人・現地社員・公認会計士など)
- キャリアの選択肢が増える(若い人向けに)
- 脳の活性化に役立つ(主に高齢者に)
- 英語学習について思うこと
- 英語を学ぶ目的や目標を明確にすること
目標は人それぞれで、日常会話ができれば良い・いやもっとなど。
- オールラウンドな英語能力の習得をめざすこと
世の中は、会話だけではなく、文章作成・会議・講演会に参加・読解など
- しっかりとした英語力を実に付けること
*内容のある英文を読む
*話し相手は、英語の上手下手せなく、何を話すかを見ている。
*英語で何をするか、何を伝えるかが重要
④ 英語を話すことは、特別なものでは、もはやない。
*自動翻訳機や英語話者の増加→英語を話せる優位性は、低下してきている。
→操る英語の中身の重要性が高まる。
⑤ 英語は、勉強するだけでなく、使うことが必要
*INPUT ↔ OUTPUTの相互作用
*Native Speakerとの接触する機会を持つ(英語を使う機会を多くする創意工夫)
⑥ 現在は英語を勉強するには、恵まれた環境にある
*インターネットの普及で英語に生の英語に接することができる。
勉強する側の努力次第
⑦ 雑学をする→英語の幅を広げる
*英文学者など専門家の英語に関する著書を読む
→英語を取り巻く知識が身につく
英語=骨 雑学=筋肉・神経
⑧ 「正しい英語をモットーに」を頭の隅に常に置いておく
- 今、していること
*「天声人語」(英文対照)
*「Readers Digest」
*「Time」
*「Economist」 などの積ん読
*英語ニュースを聞く
*「朝日Japan Times」(日英)なども
亀田さん(コーディネーター):では、みなさんの感想があればどうぞ。
N・Fさん:どうやって卒業後も英語を勉強したらいいのかと考えていました。ちゃんとした英文をこれからも読むことが大切とわかりました。
畑さん:毎日、こつこつとやることが必要ですね。この積み重ねと楽しく学ぶことも。
Z・Yさん:日本の英語教育では、日本人が英語を話したいと思い、始めたのでしょうね。
私は、外国につながる子どもの支援の仕事をしていますが、学校での英語の先生の使い方がもったいなあと思います。アメリカ出身の英語の先生がいても、10分ほどしか話す機会がなく、ほとんどが日本人の先生が指導していますね。
児嶋:私は、亀岡市やその他の地域がALTを入れるようになった最初から、関わっていました。文部省でその説明会があるので行ってと言われ、東京に行ったことも覚えています。もう、随分前ですが、それからも、ALTの先生方の入れ方については。まだまだなのですね。
C・Yさん:自分の子どもがしばらく日本の小学校に入り、今は中国の学校に行っているのですが、宿題はほとんど紙で、タブレットも、もらっているのに使っていないのはもったいないと思います。タブレットの子どもたちへ持たせてどう使うかの学習が必要でしょう。
M・Hさん:先生が十分、使い方がわからないのかもしれませんね。
C・Yさん:先生へのデジタル教育も必要かも。
N・Kさん:10年前に教師を退職して、今は、孫達の世話もしています。先生の悩みは時間が無いことです。6時、7時まで学校で仕事をし、家に帰って家事をすませ、10時ころから家で仕事をする日々でした。授業をするには、準備が必要で、子どもは3:30ころ下校しても、その間休み時間も、給食時間も指導が必要です。その間、鍵もあり、宿題も見なければなりません。新しい機器はいいのですが、研修が必要でなかなか時間が取れない場合もあります。先生は矛盾を抱えながら毎日指導している状況でしょう。
C・Yさん:中国では、ひとつのクラスに3、4人の先生がいて、各教科は別の先生が教え、食事時間などめんどうを見てはいません。担任の先生はいますが、大体国語の先生です。授業の中で聞かなかったら、その子どもの問題と言われています。
Z・Yさん:学校に行くと、先生の仕事が多いなあと思います。8:00には、登校指導もあり、8:30になると、先生達はいつも走って居るように思います。
C・Yさん:日本では、いろいろ改善することが好きなようですが、それにも限界があるでしょうね。
N・Kさん:ひとつを後で、入れようとすると、どこかを切らなければならないですね。
M・Hさん:昔は先生と遊んでいたような覚えがありますが。
Z・Yさん:元気ではない子どもの数も増加していますね。特別支援教育の必要な子も増えて。先生が足りないですしね。
N・Kさん:学校に外国につながる子どもがいれば、Z・Yさんのような先生がいたら、先生も安心だと思います。
C・Yさん:日本の教育を批判するつもりではないのですが、この構造の内部だけにいたら、見えないことがあり、それをどうやって見直すのだろうかと心配です。
N・Kさん:膨大な仕事に自分の生活を奪われ、心を病む先生が普通にいる状況です。カウンセラーの方との連携も必要でしょうね。もう量的にパンクですね。
畑さん:私は、小学生から、学校で英語を学ぶ必要はないと思っています。それよりも先に日本語をしっかり先にやり、自分を確立させることが必要と思います。もっと英語をと思う親は、それぞれに英語学校に行かせたらいいのです。好きこそものの上手なれと言われていますから。
C・Yさん:私は2月のGlobal Sessionのゲストですので、そのつづきはまた、その時にやりましょうか?
畑さん:私は、亀岡の内丸町に生まれ、大学は同志社で、家から通学していました。英語も話せるようになりますよ。
亀田さん:ここへ来るまでに、嵯峨野線に乗りますが、二条駅でアナウンスがあり、日本語で「遅れます」と言うのを聞いたのですが、その時は英語のアナウンスはありませんでした。日本語がわからない人はどうしたのだろうと心配になりました。
さて、時間が12時半を軽く超えてしまいました。もっと感想が在る人は、児嶋さんに送ってください。