2024/12/29
2024年12月25日(日)第382回グローバル・セッション・レポート
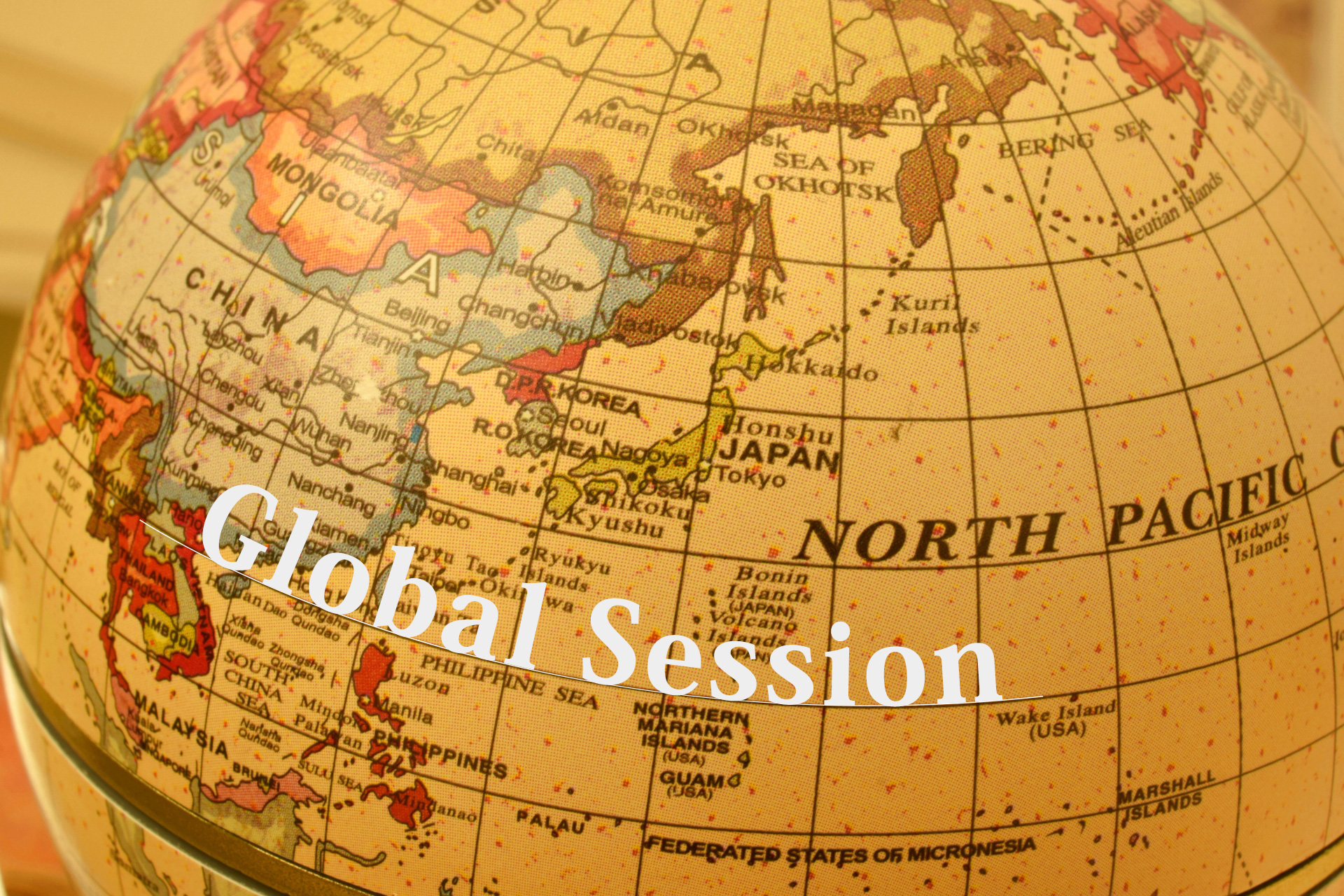
開催日:2024年12月25日(日)13:30~15:30
場所:ガレリア3階 第1会議室
ゲストスピーカー:ゲスト:村田英克さん(中国出身・日本語教師・母語支援員・ひまわり指導者(JT生命誌研究館 表現を通して生きものを考えるセクター研究員)
コーディネーター:亀田博さん
参加者:11名
今回のタイトル:「食草園から学んだ“もちあじ”」
自己紹介
亀田さん:村田さんは、今回が3回目ですね。毎年楽しみにしています。
それでは、みなさんの自己紹介からお願いします。
M・Aさん:ブラジル出身で、大本本部にいます。日本には9年目です。
M・Yさん:亀岡在住です。「食草園」の「食」とは、誰が食べるのですか?
村田さん:例えば、笹や竹はパンダの食草と言えると思いますが、今日は蝶々と、蝶々の幼虫が食べる植物のお話です。
R・Sさん:ひまわり教室の学習支援をしています。
M・Kさん:京都の中京区から来ました。10月に新聞に館長の永田和宏さんの食草園のお話しが載っていて、その後、植物園に行ってきました。
E・Tさん:今月から新しい場所で働くことになりました。JTプラントサービスという所ですが、これも、JTということでびっくりしました。先週の水曜からかぜでダウンしていました。
Y・Hさん:総合商社を退職後、2年前ですが、その後、5050年ぶりに亀岡に戻って来ました。このGlobal Sessionは、頭の刺激になり、楽しみで参加しています。今回も、「食草園」というふだん、聞けない話が聞けると思って来ました。
R・Eさん:昔、交流活動センターであった、グローバルパスポートという企画に参加していて、今回、新聞で見て参加しました。私は、30年間、「たんぽぽ」として絵本やかみしばいを作っていて、『さんしょとみかんの木』などもあり、楽しみです。
K・Yさん:ひまわり教室で本の読み聞かせを担当しています。もう10年間過ぎたようです。生きものが好きで、前回の村田さんのお話しにも参加しました。
児嶋:このGlobal Sessionは亀岡交流活動センター時代に始め1999年からですので、20年以上になります。今回も村田さんのおもしろいお話しとセッションをお楽しみください。
亀田さん:私は、まだ高槻のJT生命誌研究館には行ったことがないのですが、いちど行きたいのですが、いつの時期が一番いいですか?
村田さん:食草園は、5月か6月が一番いい感じですね。それから秋、蝶々は、だいたい11月以降は越冬モードです。
亀田さん:この資料にあるように、たくさんの蝶々が来るのですか?
村田さん:これまでに確認したのはだいたい20~30種くらいでしょうか。私たちの日常の生活圏にも重なるまちなかで見られる、身近な、小さな自然に目を向けるところから私たちヒトという生きものも含めた生命にとっての豊かな環境を考える、その入り口として、生命誌研究館では食草園を提案しています。
高槻は街、「とかいなか」で、市の面積のおよそ半分は山地です。山を越えると亀岡にもつながっていますね。高槻市のいま一番のニュースは、関西将棋会館が市内で12月にオープンしたこと。市域の山林の木材から拵えた将棋の駒を市内の小学校にプレゼントしたり、市は「将棋のまち」をアピールしています。うちの子もその将棋の駒をもらってきました(笑)。
研究館の場所はまちなかですが、近くに芥川も流れ、山へ続く自然を背景に、住宅地でも、皆さんお庭にみかんやホトトギスなど植えますし、街路樹を伝って蝶々が食草園にもやってきます。蝶々は種類によって、移動距離は違うと思いますが。
皆さんよくご存じの渡りの蝶々:アダギマダラは、暖かいアジアの方から海を越えて日本列島を縦断して北海道まで、毎年、行き来しているようです(夏は北へ、冬は南へ)。その道行きの一コマを高槻でも見られますし、亀岡でも見られるのではないでしょうか。
- JT生命誌研究館の表現を通して生きものを考えるセクターの立場から>
私(村田英克)は、長年、JT生命誌研究館(現館長・永田和宏)で、主に、展示・映像・出版物を企画・制作・編集して「生きものってみんなすごいね!」「生きもの研究ってこんなに面白いよ!」とみなさんに向けて表現することをお仕事としてまいりました。なかなか他にない珍しいことをやっている、やらせていただける、恵まれた職場だと思います。何をやっているのか? 少々、ややこしく言いますと「生命科学研究(発生・進化・生態系)の知見を、誰もが、自分事として受け止めてくれるような(私たちヒトは生きもの、自然の一部ですから)コンテンツを拵えて、それを介して、生きものとして暮らしやすい豊かな社会の実現への共感の輪を広げる」という思いでやってます。
今日のお話の「食草園」は、およそ20年前に、チョウと食草の関わり合いながらの進化の解明を目指す新しい研究がスタートしたことを受けて、その研究を伝える生態展示として、施設4階の屋上に作られました。チョウの幼虫が食べる植物をそろえた食草園です。屋根はなく、市域から蝶々がここへやってきて、卵を産み、幼虫が育ち、蛹から羽化し、また旅立って行きます。但し、トリやハチなどの天敵もやってきますし、アブラムシやダンゴムシも棲む、まちなかの小さな生態系のサンプルです。20年前の最初の担当(庭師?)が私でした。今は、若いスタッフたちが日々手入れをしてくれています。
2年前に、このGlobal Sessionでも皆さんに鑑賞していただきましたが、ちょうどコロナの時期に、この「食草園」にまつわる昆虫と植物に関する研究館の活動を伝える記録映画を作りまして、それは全国のミニシアターでも上映していただきました。私は、元々、映像制作の仕事を長くしておりましたので、コロナ対策で、人と人とが会うこと自体が憚られ、催しの開催なんてとんでもないという時期、私は「昔取った杵柄」で、なんでもかんでも映像に記録して自分で編集して発信するということを始めました(業者さんに頼むとコストが嵩みますが、私は、ほぼ人件費のみです)。それが劇場向け映画としても受け入れられたことは、大変、嬉しいことでした。そもそも若い頃は、学校へ行かず、映画館に入り浸り、映画を浴びる日々を送っておりましたので。
- 小学校のPTA活動として>
そして次は、昨年のGlobal Sessionで、これまた記録映像として、皆さんにもご鑑賞いただきましたが、ちょうど「食草園」の映画上映であちこちお招きいただいていた時期に重なりますが、たまたまPTA会長を引き受けた、愚息の通う小学校が、なんと創立150周年だというのです(なるほど明治の夜明けののち、鉄道が敷かれ、寺子屋が学校に、そこから150年)。その記念に、小学校の学校生活を描く短編記録映画を作って、全校児童の保護者の皆さん、先生方や地域の方々にご鑑賞いただきました。PTAを引き受ける以前から、子どもが持ち帰る宿題やら参観やらを通して、大変、充実した学校生活を送っているなあと感心し、私自身が興味を持っておりましたので。この映画に出て参りますが、この町は、中世以来の寺内町で、江戸初期には酒造りで栄えました。また人権活動にも長い歴史があり、そうした地域の伝統や歴史を学ぶ授業がたくさんあり、まちの方々も暖かいのです。そのような歴史を背景に、子どもたちの生き生きした姿を映像にしてお伝えしました。
さて、この小学校の150周年のセレモニーを経て、研究館の「食草園」の映画もご覧になった校長先生が、「周年記念に、小学校にも食草園を作りたい、校内の池もビオトープとして再生させたい。」とおっしゃいました。「是非是非、喜んでご協力しますよ!」と、小学校の食草園プロジェクトが始まりました。学校からの提案が「緑の基金」に採択され、予算を獲得。市役所の協力と、プロの造園ボランティアの積極的な参加も得て、5年生が中心となり総合的な学習の時間、約30時間をかけて、庭づくりが進みました。そして私は、もちろんその授業の様子も記録撮影し、関係者で鑑賞いただける記録映像に仕立てました。今日は、その記録映像を、後ほど、ご鑑賞いただきます。
さっき、申し上げましたように、私は「コロナの時期に、なんでもかんでも映像で記録し、発信し始め」たのですが、私の拵える映像は、こちらが予め考えた意図に沿って形にしていくのではありません。研究館の人々にしても、小学校の子どもたちも先生も地域の方々も、そして町の佇まいも、空も、自然も、みんな楽しそうに、日々、自分たちのやるべき活動をしている。私の役割は、カメラを向けた先で起きている人々、人に限らず全ての生き生きした様子、元気いっぱい、楽しそうに、一生懸命、生きている人々、物事を、そのまま、掬い取ってくること、そして掬い取った映像の声を聞きながら、何が起こっていたのかを、この映像を見た、何も知らない方々に届けるために、見ていただけそうな試聴時間の枠の中に収める、流れを作り出す(映像の本質は、目と耳で追う、飽きることのない動きの連鎖です)。時間と空間を再構成します。それは、映像に映っている物事の命を、謙虚に、かつ楽しく、紡いでいくことと言っても良いかもしれません。作品の意図、伝えたいことというのは、カメラが捉えた映像の中にあります。それをグッと取り出して、伝わるようにするのです。そういうことを、いろいろやっておりますと、出来上がった映像に関わる、まずは当事者の方々、そして、そのような活動に興味を持っている方々には、大変よろこんでいただける、ということがわかりました。
- オンライン活動写真館「みんなの “もちあじ”」とは>
そんなに、皆さん、喜んでいただけるのであればということで、研究館での仕事、PTAとしての地域貢献に加えて、第三の仕事として「オンライン活動写真館 みんなの “もちあじ”」なる動画配信サイトを立ち上げ、市内のNPOサポートセンターに団体登録し、さまざまな市民活動=自然保護、子育て支援、親子劇場などに取材し、皆さんの素敵な活動を、多くの方々に知っていただくために、動画発信によるお手伝いを始めました。12 月で、ちょうど丸1年になりますが、既にいくつかの団体さんにお声がけいただき、映像でお手伝いしたり、今、私が住む地域の歴史、伝統文化を次世代に映像で伝えよう!というプロジェクトも動き出しました。いろんな動画があるんですが、一番、多く見られているのは蝶々やイモムシのショート動画で、これはPTAで小学校へいくたびに四季を通じて変化する食草園の様子や、ベランダの食草園の様子などで、こういうものはアクセスが上がるようです。人間社会の営みも、虫や草花の営みも、「もちあじ」という言葉で括ると、矛盾なく一つにおさまるように思っています。
「もちあじ」という言葉を、私はとても大切に考えています。これはPTAの立場で、このエリアの学校と地域が一体となってこれまでも取り組んできた、小中学校の一貫教育の基本「誰一人取り残さないまち」を実践する入り口の言葉で、これを知って、ちょっと感動してしまいまして、小学1年生の「もちあじ学習」からお借りしました。1年生は、まず自分の「もちあじ」を書き出します。それを皆で発表しあって、お互いの「もちあじ」を認め合うことから学校生活が始まるのです。良い悪いじゃないのです。不得意なことを書いても良いのです。「ドジ」とか「めんずき」とか「はしるのがはやい」「ほねばっかり」とかで良いのです。それをお互いに話し合うことによって子どもたちは、自分とは違う異質な存在を受け入れる心を養い、多様性を前向きに捉える学習が始まるのです。9年生(中学3年生)まで続きます。私はこの「もちあじ」という言葉が、生命にとっての本質だと思っています。生命誌研究館が、科学の言葉を借りて、積み上げて、いろいろ語っている、その行き着く先は、詰まるところ、この「もちあじ」を認め合う世界なのだと思います。私は、齢60にして小学校に学んだこの言葉を羅針盤として、第三の活動として市民公益活動にも取り組んでまいりたいと思っています。
===========<パワーポイントを使っての紹介>===========
・生命誌研究館の活動の基本と、「食草園」の紹介。
〜どんな草花があり、どんな蝶々がやってくるかなど〜
・研究館からの提案により、他施設に最近作られた「食草園」の例
〜京都府立植物園「いもむしのレストラン」
〜高槻市役所敷地内「チョウと幼虫の食草園」
〜JR大阪駅前の公園計画の中で、その一角に作られた「うめきた食草CUBES」
・食草園と言っても、それぞれが、個性的な他にないお庭になっています。
・小学校の食草園プロジェクトの紹介
〜その記録動画の鑑賞
============ =========== ============
質問開始:
Y・Hさん:「食草」ということばは、重要な役割を示していると思いますが、気候変動で各地の植生にも影響が出ていると思います。一般にガーデニングも流行っていますが、「食草」に重点をおいた庭づくりというのは今、どれくらいあるのでしょうか?
村田さん:街路樹でも、花壇でも、「まちなか」では、どうしても人間が管理しやすい植物、入手が容易な植物、あるいは消費者の購買意欲をそそる植物が、普及しているのが今の社会の実情かと思いますが、本来は、その土地の元々の植物の分布などを意識したいですね。難しいですが。
生命誌研究館は「生命論的世界観に基づく「科学的知」の創造と、その社会への還元」をミッションとして活動しています。私たちヒトも、現在、地球上に生息している多種多様な生きものの一つに過ぎず、そのような謙虚な立場から、自然界を構成する生きものたちとの「共生」「共存」を考えていきたい。ということを研究館の展示や映像や季刊誌やらで、一般に呼びかけていくというお仕事をしてまいりました。たとえば植物たちは、葉っぱを広げてお日さまを浴びて光合成し、根っこで土から養分を得てと、そういう生き方をしています。土中の微生物は、さまざまな有機物を分解し物質循環に大きく貢献しています。一方、私たち動物は、他の生きものの生命をいただいてそれを栄養として生きています。他の生きもののいのちをいただいているわけで、それで私たちは3度3度の食事に際して「いただきます」というわけです。そこには感謝の気持ちが込められているはずです。その時、善・悪の価値でなく、多種多様な生きもの同士が、一体どのように関わり合っているのかということは、まだまだわかっていないでしょ。という謙虚さを自覚した立場から社会を経営して行かなくてはいけない。日常生活の一コマ、一コマにおいて「生命論的世界観」を振り返る、その小さなきっかけとして、まちなかでも可能な、蝶々が訪れ卵を産み、その幼虫が食べる植物をそろえた食草園を身近に作って、小さな生きものたちの関わりあう様子を見つめるという提案をしているわけです。
もう一つ、先ほど映像でごらんいただいた、小学校内に「チョウを呼ぶ庭をつくる」プロジェクトでご一緒した「まち杜の環」という造園家のグループ(LLP)の方々のお仕事ですが、まちなかでの「循環」の庭づくりを提唱し、そして実践されている。小学校の食草園プロジェクトでは、私は、チョウと食草についてのアドバイスをしながら、プロジェクトの一部始終を記録撮影して一つの短編映像にしました。今回は、小学校の敷地内でしたが「まち杜の環」では、都市の中の施設でも、個人宅でも、とにかく、ゴミを出さない、土が豊かになる庭づくりを実践されています。ダンゴ虫やミミズが棲みつき、土壌生物が有機物を分解し、植物にとっても私たちの生活にとっても、豊かな自然を身近なところに作って行こうという。小学校では、まず「循環」を考える授業に続き、皆で校内で落ち葉を集め、これは堆肥やマルチングに使えます。土中に水や空気が通って、生きものが暮らしやすい土づくりを実践、木陰に廃材を再利用したベンチを作り、全校児童で、蝶が蜜を吸う花を咲かせる植物やイモムシの食べる葉っぱが茂る植物(食草)を植え、昨年の修了式前、2月末に完成しました。そして、4月以降、植物たちは生い茂り、花開き、たくさんの蝶が訪れ、ダンゴムシやミミズも棲む、とても素敵な庭になりました。もっともその手入れを続けていくことが大事ですが。研究館の「食草園」の提案や、まち杜の環の「循環の庭」の提案は、まだまだ始まったばかりですが、こうした取り組みが、これからもっと浸透していくことを期待しています。
Y・Hさん:人間は、いろいろな物を食べていますからね。
R・Sさん:「食草」という発想がおもしろいと思います。楠(くすのき)を食べる虫もいますね。ジョチュウギクはどうですか?
村田さん:蚊取り線香の原料ですね。キクを好んで食べる蝶々はあまり聞いたことがありませんが、ヨモギは、ヒメアカタテハの食草ですね。
R・Eさん:イモムシは、さなぎで越冬するのですか?
村田さん:蛹が多いですが成虫で越冬するのもいます。幼虫で越冬するのもいます。エノキを食べるゴマダラチョウの幼虫は、夏場は葉っぱに紛れてみどり色で、冬場は落ち葉、枯れ葉に紛れる茶色になって越冬します。
Y・Hさん:民間企業が生命誌研究館を作ったのですね。JTさんが、作られた理由は?
E・Tさん:ぼくがこれから仕事をするのもJT関連ですが、組織図の中にあったような気がします。
村田さん:生命誌研究館は昨年が創立30周年でしたが、元々、たばこの工場があった土地で、そこで新たに医薬総合研究所ができることになり、その敷地内の一角に、市民に開かれたもう一つの研究施設として設立されたと聞いています。中村桂子名誉館長が、それまでの博物館とは違った新しいコンセプトで、生きもの研究(生命科学)の魅力を一般の方々と広く共有するための活動拠点として構想されました。今のSDGsを先取りした構想を実践する組織として、JTグループの一員として活動しています。
村田さん:以前、亀岡から見学に来られた時に児嶋さんから、第一声に「なんでJTなの?」と聞かれたことを覚えています。
児嶋:見学に行った時に一番おどろいたのは、屋上に、庭園があったのです。高槻の蝶々のためのレストランと言われて。驚きました。
亀田さん:以前、村田さんが来られた時に小鼓を聞かせてくれましたね。あれを聞かせてください。能の世界の豊かさですよね。
村田さん:最近は、ちょっとお能の囃子方のお稽古はサボってまして、なかなかお金もかかることなんで、今は距離を置いています。で、最近は、江州音頭にハマっています。「もちあじ」動画の取材で、富田のエリアには、珍しい、陰旋律の江州音頭の伝統があって、その文化を映像で残そうというプロジェクトで、今その音頭とりの師匠や、踊り手、太鼓の方などに取材をしているところです。お囃子もそうですが、やはり、自分で踊ったり、謡ったりしないと本当にはわからない、体に入ってこないと思うのですが、今はまだその入り口でウロウロしています。
M・Kさん:江州音頭は滋賀のおどりですね。
村田さん:滋賀の八日市が本場の江州音頭のようですね。この芸能の歴史を追いかけていくと、河内音頭や、泉州音頭など、関わりが見えてきて面白いんですが、あんまり広げたら収集つかないんで。
亀田さん:では、時間ですので、終わりにしましょう。(3:30を過ぎました)
