2025/03/03
2025年2月11日(火・祝)第384回グローバル・セッション・レポート
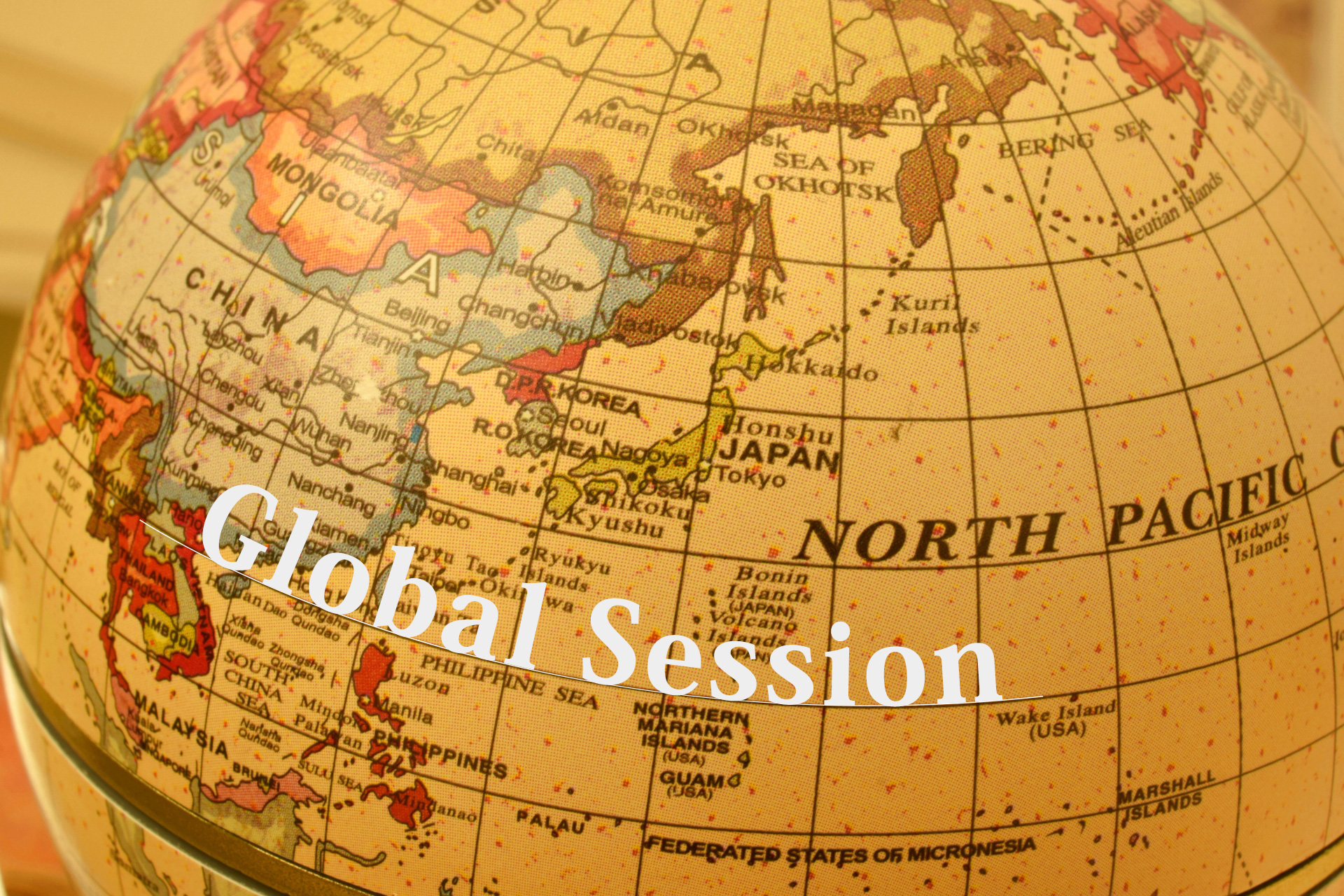
開催日:2025年2月11日(火・祝)10:30~12:30
場所:ガレリア3階 会議室
ゲストスピーカー:ゲスト:周悦さん(中国出身・亀岡市多言語指導員)
コーディネーター:亀田博さん(ツアーコンダクター)
参加者:17名
今回のタイトル:「外国人ママから見た日本の小学校の不思議」
自己紹介
亀田さん:コーディネーターの亀田です。参加者の方々の自己紹介から始めたいと思います。
M・Mさん:「やさしい日本語を広める会」の会長です。仕事をする外国人の方と接する方々も必要です。
M・Yさん:教育委員を7年間していました。今回の「日本の小学校の不思議」というタイトルに興味があり参加しました。
Z・Yさん:亀岡市で外国につながる子どもたちの教育支援の仕事をしています。周悦さんの話が楽しみです。
S・Fさん:先月、「ひきこもり」の研修会を受講しました。15才~65才くらいのひきこもりの方は、150万人ほどいるそうで、ちょうど京都市の人口くらいです。外国の方の観光も増えていますが。
Y・Hさん: 総合商社に勤めていましたが、2年前に亀岡に戻ってきて、今は無職ですが、Global Sessionは、いろいろ聞けて楽しいので、いつも参加しています。
M・Hさん:30年ほど、亀岡市内で「へき亭」を運営していました。今は無職です。ただ、家で時々、料理教室などもしています。
S・Gさん:2024年9月まで5年間、亀岡市国際交流員をしていました。今は、「森の京都」という会社で、南丹地域などの地域振興の仕事をしています。
F・Kさん:滋賀県で35年間養護学校の教師をしていました。退職後、10年ほどたちますが、今は京都の中京区に引っ越しています。
N・Fさん:亀岡市の職員です。ボランティアで京都駅などでガイドをしています。
S・Yさん:ここの多文化共生センターの相談員をしています。
Y・Uさん:小学校で、30年間教師をしていました。日本に来ている外国につながる方も増えていますが、気が付かなかった事も多いので、今日は、参加しました。
S・K(新聞記者)さん:児嶋さんに誘われてこのGSに参加しました。小学生と今度1年生になる子どもがいます。
M・Sさん:亀岡に住み、小学校の教員をしていました。10年以上前に退職し、時間が経つのが早いと感じています。いろいろなボランティアをしていますが、ひまわり教室も参加しています。今日のタイトル(小学校の不思議)に引かれ、参加しました。
K・Nさん:村おこしの仕事をしています。学童保育も2ヶ月に1回ほどやっています。前回も参加しました。
H・Mさん:亀岡で木綿の生地屋をしています。
児嶋:このGlobal Sessionは、1999年に宮前町にあった交流活動センターで始め、私が退職後は、主宰をしています。今日は、384回目です。月に1回やってきたので、もう20年以上になりますね。セッションが主なので、どうぞ。いろいろなご意見を。
グローバル・セッション スタート
亀田さん:亀岡でない所から来ていて、大津市からです。京都駅も外国人観光客が多く、この嵯峨野線も多いので、早く行かないと乗れないくらい混んでいますね。
では、周悦さんの自己紹介から始めて、今日のお話をお願いします。
周悦さん:時間的には、30分~40分話し、セッションということでいいですか?Global Sessionのゲストに呼んでいただき、光栄です。みなさんのお話しも聞きたいと思います。
私は、中国の江蘇省の蘇州市で生まれました。亀岡市の友好都市でもありますね。
自己紹介:2009年に熊本大学に交換留学で来て、2011年には京都大学大学院で発達心理学を学び始めました。現在は、英会話教室の経営と講師をしています。
保津小学校ETTボランティア講師や、東輝中学校での語学支援員をし、通信教育で「認知心理士」資格取得のため勉強中です。又、二児(3才と7才)の母です。
7才の娘(小1)は、本が好きで新聞も読んでいます。2024年4月に入学しました。1学期には、先生からも友達とも仲良く、学校の勉強もいろいろ上手にこなしていると言われていました。ところが、9月になると、学校に行きしぶり出して、母子登校や父子登校でしか行けなくなりました。今は、転校を考え、2月からは、西別院小学校に週一回行き、「ここに行きたい」と言うようになりました。このように「学校に行きたい」と思えるまでに何があったのかを探ってみたいと思います。
タイトル「外国人ママから見た日本の学校のふしぎ」ですが、中国の学校と比較して、何がこうなっているのか、みなさんといっしょに考えてみたいと思います。
中国では、成績のランキングがはっきりしています。テストを返して貰うときも成績順で呼ばれ、先生からも友達からも重く見られます。また、親の送り迎えが必要で、小学校では、国語、算数、社会、理科だけで、家庭科や生活はありません。また、成績がトップの人がクラス長になり、班長も成績順になります。運動会は、運動ができる子どもだけが参加します。入学式も子どもだけが参加し、保護者は帰ります。全校の式典も先生の話を聞くだけです。
このような中国の学校で育った私ですが、日本の学校は楽しみでした。
子どもも行く前からわくわくしていて、楽しみでした。ところが、いろいろ準備も含め頭がいたい現実がありました。
- 持ち物にすべて名前を書く。袋のサイズまで規定がある。筆箱の鉛筆の本数も。
- びっくり仰天の教室の現実授業参観:先生が二人・子どもが歩き回る
- 保護者として:PTAの集まり・授業参観・懇談会・運動会の参観など(保護者も休んで参加するほど忙しい) 中国では、1年に1、2回
デメリット:自分で考える必要がない。子ども自身の思考力が失われるのではないか?
2学期から、不登校が始まった。
母子登校をして気づいたこと:学校が楽しくないと思った現実
*先生に「おんぶして~」って言ったらダメと2回言われた(教師と生徒との体の接触は制限されると)→人間らしい行動がダメ?
*知り合いの好きなお姉さんの教室に行けない。→他の学年の階や教室に行ってはいけない。 (日本ではことばで、「大好き」と言いにくいのか?トラブル防止は、人間関係の薄さにつながらないか?)
*ブラックスケジュール?
毎週金曜に、学習予定表が配布され、下校時間が週によってちがう場合がある。(働く親は、どうやってスケジュールを組むのか?パートだけ?長期の休みの前後は給食がない。日本では予定の変化が多すぎる。→ストレスがたまる?
中国では、スケジュールの変化があまりない。
- 2年生: 2:35下校
- 2年生~6年生: 3:25校
放課後、担任の先生が教室内で預かり、決まった時間に下校する。
日本の場合、変化が多い→先生の負担にならないか?
(中国では、毎週の予定が決まっている。)
小学校の一日のスケジュールの変動で、困る児童がいるのでないか?
(気づかれないストレス・不登校につながる恐れも)
*日本の小学校の1日のスケジュール
①次の授業までに5分で移動(お茶・トイレ)
②給食は12:05から~12:45(朝ご飯が7:00でお腹がすく)
③昼休み 12:45~1:00(たったの15分)
ちょっとしか遊べない・外遊びは間に合わない
*中国では、昼寝の時間がある。(リクライニング椅子のある学校もある)
授業の間は10分と固定されている。
昼食と昼休みを含む時間は、長くて2時間も
*日本の学校でも、昼寝の時間の導入をする学校もある。
最後に、これから学校があるべき姿について考えたいです。私はまず学生は学生である前に「人間である」と思います。エリクソンの発達段階理論がありますが、6才~13才は勤勉性が求められ、身に付けたことに励む必要があると言われています。なので、学校は必要です。
ただ、学校は何を優先させるべきかというと、マズローの人間性心理学にあるように、まずは「生理的欲求」を満たす、つまり十分な休む時間があり、給食は落ち着いて食べられる環境が必要である。安定した学習スケジュール、友人・教師との関係性を作れる環境を整える。そのうえで、勤勉して成績が良い子はどんどん伸ばしてあげて、自主性を尊重して、学校のルール作りや学習内容も任せたらいいと思います。
質問
Y・Uさん:夜寝るのが遅いから、昼寝をしたいのですか?
周悦さん:政府が睡眠時間について調査しようとしているようです。不登校になった子どもは、「学校に行きたい」と思っていて、西別院小学校に行ったら、「学校が楽しかった」と言っていました。その前は、運動が好きな子どもなのに、「体育が楽しくない」と言っていたのに、この学校へ行ったら、「体育ってこんなに楽しいのかと思った」とも。
M・Hさん:中国も小学校と中学校は義務教育ですね。
M・Sさん:なぜ、どの品物にも名前を入れるかというと、落とすと名前がないと拾わないからです。昔は、私が50年前に教師を始めたころ、雨が降ると学校に来られない子どもがいました。家庭訪問をすると、家に傘が一本しかなかったのです。それで、雨がふると傘が余分にないので、学校に来られないと。今は落とし物係が居ても、だれも取りに来ないので、落とし物が溜まります。子どもの物に対する価値観がないように見えます。
先生の立場からすると、必要な物をそれぞれがそろえて置かないと授業が成立しない場合があります。
Z・Yさん:なぜ、日本ではどれにも名前を書くのかですが、中国では、自分の物はそれぞれが管理し、授業中に立ち上がったりもしないで、ビシッと座っていて、落としてはダメと子どもも思っています。
Y・Hさん:今は若いころとちがって、物が溢れています。私は、物が不自由なころに育ちましたが。無くしても買えない時代とちがって、物を大切にする感覚が低いのではないですか?中国の成績第1主義は、むかしからですか?
周悦さん:1980年代からエスカレートして来たと思います。学歴が仕事に関わり、行けるポジションも決まってしまうので、良い学校へと思うようになったのでしょう。成績のトップの人は、学校でも権力があります。
Y・Hさん:北京大学への志望者が多いと思いますが、地域別に北京大学に入れる人数を割り当てていますか?
周悦さん:割り当てる人数の違いよりも、地域によって同じ大学に入学するための合格ラインが違います。
S・Yさん:おんぶしてと言ったり、上の学年の好きな人のクラスに行けないなど、日本では人間らしい行動がだめと言われているような気がしますが、中国ではどうですか?
周悦さん:気をつけていることはあると思います。同じ性の先生に「おんぶして」とか。ただ中国では先生は権威がある存在なので、そもそも子どもはボディタッチしたがらないと思います。
M・Sさん:教師と子どものボディタッチは当たり前で、世話をすることも教師の仕事で、足りない場合は、補助の先生もつきますし。でも、コロナ禍になってから、「さわっちゃだめ」と言われ始めましたね。
H・Mさん:管理社会が子どもの社会にも入ってきているのでしょうか?自然を学べる年齢は小学校の間でしょうが、ほったらかしで育ってきたわれわれですが。昼寝のリクライニングシートにはびっくりしました。親が子を管理するのはおかしいと思います。
オーストリアに長く住まれているF・Mさんは、親と子の絶妙の距離感を持っておられます。中国では成績だけでいろいろ決めるのですか?バランスが必要と思いますが。今日は、リクライニングの椅子などが中国にあると聞き、日本にはないことも学ばせていただきました。
S・Gさん:カナダでは、文房具も含めて名前は書かなかったと思います。無くしたら、先生か誰かに借りていたと思います。鉛筆削りもあるけれど、音がして、はずかしかったと覚えています。成長していくので、世話をしすぎないことも大切かとも思います。
Z・Yさん:学校によってちがうかもしれませんが、日本では放課後預かる場所もあり、7:00までできると思います。中国では、自分の場合は、家庭科もあり、工場見学などもしました。昼寝の時間もありました。眠たくない子はどうしたかというと、絶対に寝なければならいと言われていたと思います。
S・Fさん:会社にも昼寝の習慣はあるのですか?
Z・Yさん:私の子どものころは、給食はなかったです。でも学校に食堂はありました。食べに帰ってまた来る子もいました。今は学校に給食はありますが、どちらにするかは選べると思います。日直は、班長がやり、毎日指導します。日本は、毎日替わりますね。私が行っている千代川小学校などでは、先生も子どもと遊んでいると思いますが。時間割は、中国では1年間同じですが、毎週変化する日本の時間割の方法は、先生もたいへんだろうと思います。
S・Fさん:先ほど先生におんぶしてもらえないとありましたが、先生にゆとりがなくなったこともあるのでしょう。時間割も、いつごろから毎週出して、変わるようになったのでしょうね。
F・Kさん:教師も心の病で休む人がとても増えました。1990年ころからです。高校でも進学校の教師はたいへんです。テストでも成績によって席が替わることもあり、自分がつぶれないようにするのもたいへんでしょう。教育大学を卒業しても教師にならない人が増えてきたと聞いています。中国では先生の病気はありますか?
周悦さん:中国でも先生はたいへんです。先生の教育に集中できる時間が少なくなっています。国からは、国を協賛しましょうというような知らせを生徒に送ることも言われます。
Y・Hさん:教育も大事ですが、まず、人間性ですね。物事にひとつの解決方法はないと思います。
M・Yさん:先生も管理されています。中国でも日本でも子どもを大切に育てたいという思いは同じでしょう。中国は、デジタル化が早いですね。
周悦さん:集中度を見る機械もありますね。
亀田さん:「中国の領土は?」などとAIに聞くと、答えないで、イチテンポ置くようですね。日本人はAIに弱いかもしれませんね。
児嶋:学校によって教育委員会などからの指示がちがうことは、日本ではないと思います。今までの学校と西別院小学校のちがいは、まず、子どもの数と、もう一つはどこからも受け入れる学校体制を持っているので、自分と同じように、親の国がちがったり、よそから来ていたり、ちがうひとがたくさんいることではないでしょうか?それに子どもの数が少ないので、学年を超えてなかよくなっていこうという雰囲気はあるのでしょうね。
周悦さん:学校にもっとよゆうがあればと思います。子どもがたくさんいても、個人差はあるはずで、いろいろな学年の子どもと遊べることも必要だと思います。実際の人間的環境のように、いろいろなひとが交ざっていますから、それが重要ではないかと。
亀田さん:12:30を過ぎましたので、これで、終わりにします。意見や質問があれば、児嶋さんを通したら、また周悦さんとの連絡がとれますので、どうぞ、よろしく。