2025/05/10
2025年4月27日(日)第386回グローバル・セッション・レポート
開催後のレポート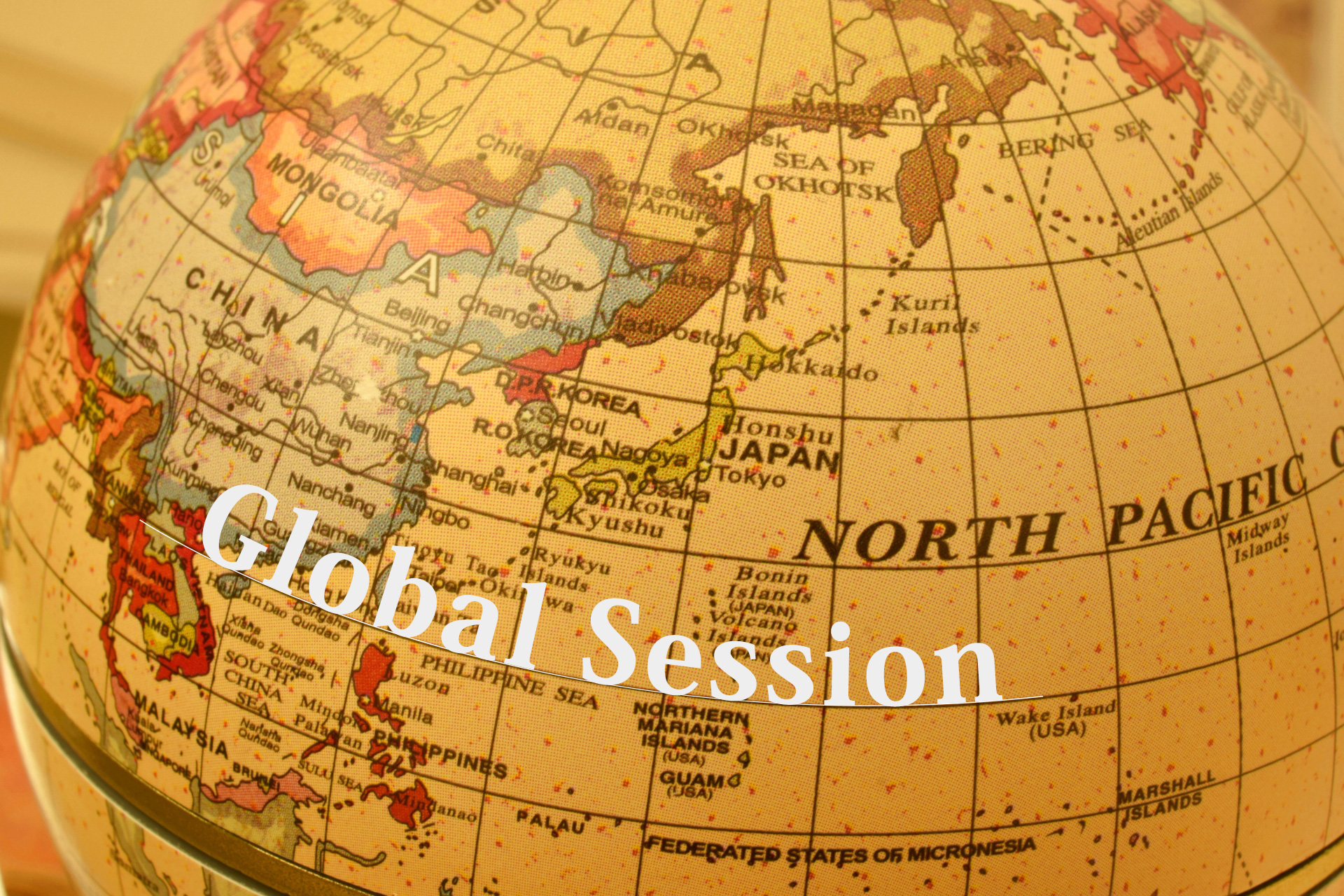
開催日:2025年4月27日(日)10:30~12:50
場所:ガレリア3階 会議室
ゲストスピーカー:山本咲さん(かめおか多文化共生センタースタッフ)
コーディネーター:亀田博さん
参加者:13名
今回のタイトル:「いろいろ考えて帰ってきました」
恒例の自己紹介からスタートです。
コーディネーター(亀田さん):では、これからGlobal Sessionを始めます。
まず、自己紹介からお願いします。
E・Tさん:2024年の8月からまた、亀岡に住み始めました。JTの子会社に勤務していますが、12月から同じ職場の中で新しくなり、悪銭苦闘しています。久しぶりにGlobal Sessionに参加しました。
Z・Sさん:亀岡市の職員でしたが、期間が終わり、新しく「森の京都」で仕事を「しています。今日のゲストの山本咲さんは、トロントから日本に家族で帰国したと聞き、興味があって参加しました。トロントは、ぼくのふる里です。山本さんが、カナダに来られた時は、ぼくは、14才でしたが、日本で出会ったのは、24才でした。
R・Sさん:オフィス・コン・ジュントの主催するひまわり教室で、指導者として関わっています。外国につながる子どもの支援について関わっています。
M・Sさん:咲さんとは長い付き合いになります。日頃から話はしていますが、どんどんテリトリーを拡げて行かれているようです。亀岡に住んで思う事を聞きたいと思っています。
M・Mさん:「やさしい日本語」を広める会の会長をしています。外国につながる人々にわかりやすい日本語で伝える方法をと考えています。
M・Hさん:立命館大学院の二回生で、日本語教育の専攻です。
Y・Hさん:いつも言っていますが、仕事で亀岡を離れていて、2年前に戻って来て今は、無職です。GSでは、いろいろな話が聞けるので、おもしろいです。(9月には、ゲストをお願いしています。:児嶋)
Z・Yさん:中国出身で、外国にルーツを持つ子どもたちの教育支援員をしています。(5月のGSのゲストです。:児嶋)
N・Fさん:市役所で勤務しています。ひまわり教室で指導もしています。
児嶋:Global Sessionは、毎回言っていますが、1999年から始め、今回が386回目になります。20年以上になると思います。
亀田さん:大津市に住んでいます。滋賀県は、琵琶湖があり、湖が中心です。大津市はマンションが多く、亀岡に来ると古い家に住んでいる人も多く、とても落ち着きます。
近江八幡や、彦根、長浜なども特色がありますが。
山本さん:亀岡はいろいろな所にアクセスがいい場所と思います。
亀田さん:では、山本さんのお話しをお願いします。
山本さん:亀岡に来て3年目になります。大阪の箕面生まれです。コロナ後、2022年に夫と合流して、家を探し、亀岡にベストの家として、決めました。
Global Sessionは、亀岡に住むようになる前に、多文化センターで、四方美智子さんに進められて参加しました。
カナダも好きでしたが、いろいろ考えて日本に帰って来ました。家族は、5人家族です。
小学6年生のノアと小学1年生になったアレンと5才のミラと夫のホルネル(42才)と咲(37才)です。
山本さんの追加のレポート
「本日は大変貴重な機会を賜り、本当にありがとうございました。児嶋さん含め、皆さまが“面白い”と思っていただけたらとても嬉しいです。
グローバルセッションのような、能動的で建設的な、それぞれの意見や思いが話し合える場所が、どの機関でも当たり前になったらなぁと改めて感じました。
いろんなことを話しすぎて、うちの子供達の言語について共有するのを忘れていました(笑)
●小6のノアは小1で日本に来たので、日本語に順応するのは容易でした。一年生の漢字も他の子供達と同じように習得しました。逆に、英語を話す環境がなくなってしまったため、英語が弱くなってしまいました。英語は6歳レベルの英語しか覚えていません。家ではパパとは英語で会話をしていますが、うまく伝えられないこともたまにあるみたいです。リスニングはありますが、単語の理解もカナダ人の6歳レベルです。
現在はアカデミックな英語学習は積極的にはしていません。家では英語で映画やYouTube 動画を一緒に観たりしています。
漢字は覚えられましたが、国語の読解力や日記を書くこと、会話力は他の子より平均以下かも?と感じたことは低学年の頃よくありましたが、言葉が遅いのも長男あるあるか?と思ったりもしました。生活上、問題ないです。
名前もカタカナですし、周りから帰国子女のように見られることが嫌みたいで、英語を少し拒絶しているようにも見ていて感じます。
まずは日本語をしっかり習得してもらって、英語に興味がでてから自分の意志で勉強してくれたらと願っています。最近は、自分の産まれた国、カナダにまた行ってみたいと言い出していますので嬉しいです。友達も多く、元気な野球少年です。
●アレン(現在小1)は日本で産み、0歳から2歳くらいまでカナダにいましたが、学校や幼稚園に通っていないので、英語は家庭内でのみでした。日本語が母語です。ただ、ノアよりも語学能力に長けているように思います。これは個人差や個性かなと思っていますが、両親の英会話をしっかり聞いているので英語も理解しています。積極的には喋ろうともしています。
●ミラはカナダ生活は4ヶ月のみなのでほぼ日本の環境で育っています。英語にふれることは両親の会話くらいです。女の子なので、口が達者です。よくしゃべります。英語はあまり喋りたがりません。英語で喋りかけても日本語で返事します。
3人とも、無理に英語は教えないようにしています。いつか自分たちが両親の住んでいたカナダや、アルメニアなどに興味を持って、外国語を学びたいと思ってくれたら、その時はサポートしてあげたいと思っています。」
なぜ、カナダのトロントに?
子どものころからのあこがれ+日本の景観がきらい(電車でみる風景ばかりですが)
はやく広い世界に行きたいと思い、アメリカ文化にあこがれていました。(ただのあこがれ)ワーキングホリデイでニューヨークの上にあるトロントに行きました。
フィリピン人の家でホームステイをしていたら、アルメニア出身の男(現在の夫)が休日に遊びに来て、それが夫との初めての出会いでした。トロントはいろいろなストリートがちがう民族性を持っている町です。
カナダは、それぞれの色や形を活かしたモザイクアートで、アメリカはいろんな素材を溶かしてできたスープ(るつぼ)みたいな感じと思います。
人種のモザイク(Mosaic):いろいろな文化や民族がそれぞれの特徴を持ちながら共存する社会。カナダのトロントでは、中国系、インド系、イタリア系など、それぞれの文化が残ったまま暮らしている。
人種のるつぼ(Melting Pot):いろいろな文化や民族が混ざり合い、一つの「アメリカ文化」に統合される社会。ニューヨークでは、移民もアメリカ流の生活になじみ、英語を話し、アメリカ文化を受け継ぐ。
人種のるつぼの由来:英国のユダヤ系作家:イズレイル・ザングウイルが20世紀初頭に発表した戯曲「メルティング・ポット(るつぼ)より
るつぼ:何種類もの金属を溶かし、一つの合金とするための道具のこと
なぜ、今日のテーマ「いろいろ考えて帰って来ました」にしたのか:
私は、大阪に生まれ、6年~7年バーテンダーをしていました。いじめられたこともあり、人間不信にもなりました。そこには、外国人も来て、英語で話すこともあり、早く海外に行きたいと思うようになりました。ワーキングホリデイでカナダに行き、3ヶ月ほどESLで英語を学びました。アルメニア人の夫と出会い、結婚をして、母親になりました。
夫はカナダの市民権を持ち、私はカナダの永住権を取得しました。その後、カナダの移民のための英語学校LINCに通い、英語をしっかり学び、人生で一番楽しい学校生活だったと思います。その後、留学サポートの仕事やパソコンを使っての仕事などもしました。
カナダの主要な移民プログラムは、言語能力(英語または、仏語)が重要な専攻基準の一つで、言語教育が移民政策の中心である。
カナダ:言語支援:ESL(英語支援)クラスが制度化
教員体制:ESL資格を持つ教員が常駐
法的枠組み:教育機関に提供義務あり
日本:言語支援は、一部学校が自主的に対応
教員体制は、専門教員の不足:自治体によって格差がある
法的枠組みは、努力義務レベル
カナダの多文化主義
カナダは人口が少ないので、移民を受け入れないと成り立たない移民国家であり、文化的多様性を前提としている。1971年に多文化主義政策(Multiculturalism policy)を国の政策として採用。人種・宗教・言語などのちがいを尊重する。
例:*移民が、母国の言語・文化を守りながら暮らせる社会をめざす
*州や市の公式文書が多言語対応(中国語・ロシア語・ペルシャ語など)
*学校で、宗教に配慮したメニューや休暇をとり入れる(ラマダン・ヒジャブなど)
日本は、単一民族国家としての意識が強い。それは、外国人が少数派で、特別扱いをされやすい。そのため、外国人の「受け入れ」に課題がある。最近は、外国人労働者や留学生が増加し、じわじわ変化中。「日本的なやり方」に同化を求める傾向がある。事実上、移民は多くなっているが、移民政策は不安定(技能実習制度や特定技能)。多文化主義の認識が不足している。また、支援の地域的かたよりがある。
例:*外国人のための相談窓口の設立(かめおか多文化共生センターなど)
*小学校や中学校での日本語指導支援(亀岡市・京都市など)があるが、多くは、非常勤やボランティアに頼っている。日本語が不自由なまま、通常授業に入ることになり、教科の学力が見につかないケースが多い。また、年令が高くなるほど「学び直し」が困難になる。そのため、言語能力が原因で進学をあきらめる生徒もいる。
*「やさしい日本語」の会などの指導(亀岡市役所などで市職員の指導のも)
教育・子育てのちがい
カナダ:自由な発想や多文化的理解が大切 個性・多様性を重要視する。そのため、個性や自己表現を尊重する。そのため、能動的な学びとして生徒が主体的に参加する授業を重視する。対話型で、質問やディスカッションを重視(Show and Tell)
考える力を育み、問題の本質を見抜く思考法として、Critical Thinking(批判的思考)が重視される。アインシュタインは、「常識とは、18才までに身に付けた先入観のコレクションである」と言い、うのみにしないで多角的に考える力が大切とする。
PTA活動は、アメリカ発祥だが、カナダにもあり、親は積極的で、ボランティア精神が根付いている。
清掃は、清掃員がする。トイレはきれいではない。ランチタイムは子どもが弁当を持って来て、子どもだけで食べ、教師はいない。
日本:知識の習得と協調性が求められる。(子どもが掃除)(給食を教師と共に)
集団の中で調和を保つ力が求められ、礼儀や秩序を大切にする。学び方は、受動的で、靜かに聞くことを求められる。
PTA活動は、会議は形式的。トイレはきれい。
Y・Hさん:カナダでは、「Critical Thinking(批判的思考)が重視される。」と言われているようですが、日本では、「批判的」という言葉のイメージから、あまり適切ではないと思われていると思いますが。
医療制度
山本さん:実は、日本の医療制度で息子が助かったことがありました。カナダではファミリードクター制度があり、予約する必要があり、時間がかかり、不便でもある。2才の時に帰国した時、それ以前から、腹痛と熱が続いていたが、なかなか見てもらえなかったが、日本では、小児科で診察後、すぐさま総合病院を紹介され、隠れた病気について、それぞれの医師たちが真摯に対応してくれて、結果、日本で無事に手術して成功しました。
カナダでは出産後、1日で退院しなければならないので、Midwife(助産師)制度があり、産後1~2日目に自宅を訪問するケア制度があります。とても助かったし、ミッドワイフの活動に母としてすごくあこがれもしました。でも、日本の贅沢な入院生活に憧れて、2人目は日本で出産しました。
仕事と働き方のちがい
カナダ:仕事が厳密に分業、専門化されている。(専門家に責任を振り分け、働きやすさを重視する。(「担当ではない」という責任の明確化
例:カナダのカスタマーサービスに電話する→「その件は、別の部署です。」→それは、別ですね。→待たされ、折り返す。または、やっと解決
サービス・ホスピタリティ
カナダ:「対話と公平さ」を大切にする文化。フレンドリーな接客など。
チップ制度:南北戦争後の奴隷解放宣言後に広まった。“感謝”だけでなく、“構造的な不平等”の影もある。
*人種差別や搾取の歴史的背景が全くないとは言えない。
*アメリカでチップ制度が根付いた背景には、奴隷解放後の黒人労働者たちへの待遇が深く関係している?
*雇用者側が「正規の賃金を支払わずに済む」仕組みとして利用された側面も。
日本:おもてなし文化は、「見えない心配り」に重きを置く文化。
千利休:「おもてなし」=「表なし」説
表裏のない心で、表面的ではなく本心で相手を気遣う
聖徳太子:「和をもって尊しとなす」
「もって」「なす」の文字が「もてなす」という言葉に発展した
見返りを求めない心・気づかれない気遣い:サービスの在り方がカナダ流と根本的にちがうと思います。
日本文化を形づくった3つの思想の融合(日本独特の精神文化)
神道:自然や目に見えないものへの畏敬
「清め」や「調和」「礼儀」を大切にする
周囲と調和して生きる心
仏教:苦しみを乗り越える智慧と、他者への思いやり(利他の精神)
無情や内省を重んじる
静けさ・控えめさ・慈悲の心
儒教:親子関係、師弟関係など上下関係や礼節を重視
勤勉・忠誠・礼儀という価値観
道徳と秩序ある社会を理想とする
トロントは、都会だけれど、どこでも簡単に行ける街で、住宅街は木が多く、歩き回るのも楽しいです。公園も多く、子どもと大人が楽しめる街。冬には、学校の校庭が雪だるまだらけになります。移民の学校も充実していて、いろんな国から来た人たちとディスカッションができ、日本人として、日本を知らなければと思いました。カナダに移民として来た人たちは、祖国は好きだけど、政治的不安などが現任で住めなかったので、自由な国のカナダに移民として住むことができて、嬉しいと言っていました。私は日本人としてカナダに住み、海外から日本を俯瞰し、自分を見つめ直す機会になりました。
カナダに移民として住むには、英語力は必要不可欠です。そのため、移民のための政策の中心は言語教育です。
亀田さん:質問の時間です。だいぶん、時間が経ちましたが、どうぞ。
M・Sさん:山本咲さんの講座は、よく分析され、まとまっていますね。プレゼンテーション能力が高いです。カナダの良さも日本の良さもわかります。その中で、帰国して「こんなはずじゃなかった」という部分もあるのではないですか?
私は、外国に住んで、日本に帰国したとき、単一民族の日本がせまくるしく感じられ、苦しかった時期がありました。このGlobal Sessionはちがいますが。
山本さん:カナダから日本に帰国したとき、日本の空港の清掃員の掃除の仕方を見て感動しました。日本では、それぞれの仕事に対する誇りを感じます。渡航前は病弱でもあり日本がいやで、抜け出したいと思っていました。大阪では、煙草を吸っていましたが、カナダではきっぱりやめました。帰国した日本は美しかったです。
M・Sさん:私が、苦しんで居たとき、「Global Sessionに来たら」と児嶋さんに言われ、参加するようになりました。日本だけど、日本ではないような場ですから。
E・Tさん:ここが、外国に近い感覚というのは、わかりますね。
山本さん:私は、日本は個性を殺す教育をしていたと思っていました。戦後、平均をつくる教育指導だったと訊いたことがあります。他の国はそれでは、成長しないので個性を尊重すると。最近は不登校の子がいても、フリースクールも増加していますね。カナダから帰国して数年経ちまので、確かに、自分のことしか考えない、世の中に無関心な日本人も見えて、縦割り社会だと思います。
Y・Hさん:世界の中で、自分の国に対してリスペクトが高い国とそうでない国もあります。第2次大戦後、自分の国にほこりを持てず、日本がきらいという人も増えたのです。けれど、日本のことを外国の人からよく聴かれます。小学生から、日本の歴史を学び直した方がいいと思います。日本語をしっかり勉強させるべきです。
山本さん:日本での方法で英語教育をしても伸びないと思います。
M・Mさん:外国の方を移民として受け入れるために、薬剤師のための「やさしい日本語」のビデオを造りました。保険証を造ったりすることもわからず、簡単に脱落する外国人の方もいますから。
Z・Sさん:外国人が多くなり、社会的に、外国人に対する視点がきびしくなっています。カナダでは、1970年に多文化主義を法的にとり入れてから、ずっと平和を維持しています。
M・Mさん:最近は、なんでもネットでしらべるだけで、偏見ももったままでいる若者も多いです。
山本さん:なんでもネットで調べられるから、いろいろ知っている若者は多いが、「選挙に行かないのはなぜ?」とか、10代や20代の人に「あなたは日本が好きですか?」と聞きたい。
Z・Sさん:日本人として日本の国についてもっと学んだ方がいいと思います。選挙の学習も。
R・Sさん:18才から選挙権がありますが、今は、中学生から選挙制度を学習します。高校では模擬選挙もやっているようです。
Y・Hさん:多文化共生という言葉の響きは、いいですね。だけど、まずは、日本人が日本のアイデンティティを確立する必要がある。多文化共生は二の次だと思います。
E・Tさん:それも態度で示す必要があるでしょうね。
山本さん:となりのひとに興味を持ってほしいですね。
Y・Hさん:英会話もいいけれど、まずは、日本語をしつかり学ぶ必要がある。日本のことをよく知ってはじめて会話ができると思います。
亀田さん:日本のことを聞かれて答えられる日本人を育てていく必要があるでしょう。
Y・Hさん:中学校から10何年も「英語のでこぼこ道」をあるいて来ました。ぺらぺら話す必要はないので、何を話しているのかに注目していきたいですね。
亀田さん:今日は、この辺で終わりましょう。