2025/08/13
2025年7月27日(日)第389回グローバル・セッション 「世界を繋げるには?」
開催後のレポート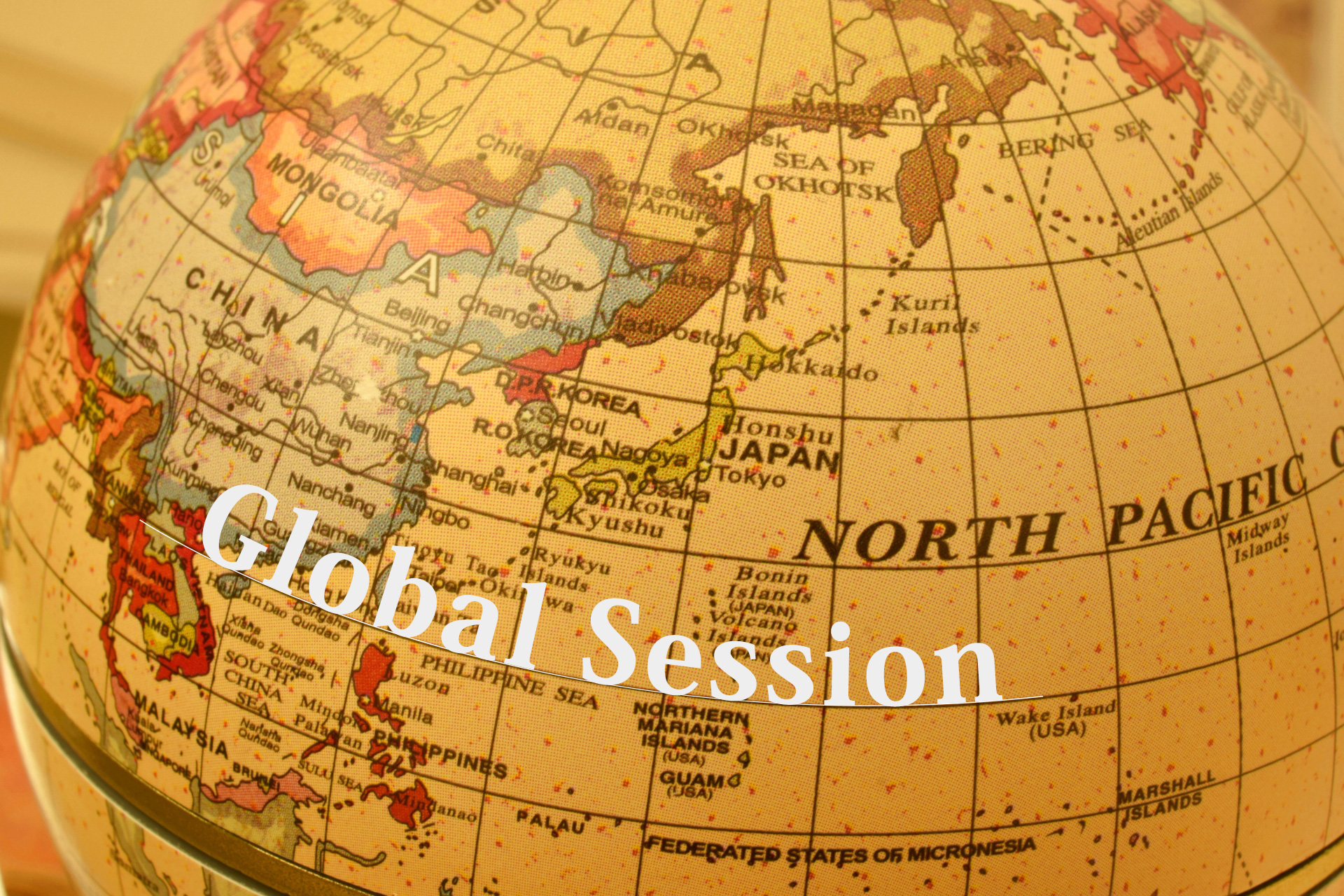
開催日:2025年7月27日(日)10:30~12:30
場所:ガレリア3階 第3会議室
ゲストスピーカー:テオ・ディアスさん(ブラジル出身・翻訳家)
コーディネーター:亀田博さん
参加者:14名
今回のタイトル:「世界を繋げるには?」
参加者自己紹介
亀田さん(コーディネーター):「ボンジーア・トードベン?」今日は、テオさんのプレゼンテーションです。いろんな事にチャレンジする方です。では、参加者の方の簡単な自己紹介からお願いします。
Y ・Sさん:台湾から来ました。今は京都の山科に住んでいます。自分の会社を持って経営しています。
E・Oさん:去年の8月に再び亀岡に住みはじめました。今は、JTの子会社に勤務しています。
Y・Hさん:会社を10数年前に退職し、今は無職です。Global Sessionに参加し、いろいろな話しが聞けてうれしいです。今日は、翻訳の話で新しいサブジェクトだなあと期待しています。
Z・Yさん:亀岡市役所の学校教育課の外国につながる子どもの教育支援の支援員をしています。テオさんとは、日本語学校で知り合いました。
H・Mさん:日本語教育の教師で、煎茶クラブにも入っています。
Guさん:ブラジルから参りました。テオさんとは、日本語学校で知り合いました。今は、社会人です。
Gaさん:ブラジル出身です。今はビザの更新中です。
Tさん:日本語学校で学習中です。ブラジル出身です。
H・Mさん:亀岡で木綿の会社を経営しています。綿で世界が拡がることを望んでいます。Z・Yさんの紹介で、Global Sessionに参加し、拡がってきました。
M・Sさん:お知らせですが、この8月24日(日)にガレリアでワールドフェスタがあります。
このゲストのテオさんにも、ブラジルコーナーで手伝っていただきます。亀岡は4つの姉妹都市や友好都市があります。(アメリカ・ブラジル・オーストリア・中国)プラス今年度は、ウクライナのコーナーもあり、5つの国のコーナーがあります。みなさんもまた、亀岡のミニ万博に参加してください。
児嶋:このGlobal Sessionは、1999年から開始し、大体月に一度開催してきました。もう20年以上になりますね。
亀田さん:私は、亀岡ではなく、大津市から来ています。JR大津駅から京都駅まで10分で、亀岡駅までは30分弱です。京都市内をぐるぐる回るより近いです。滋賀県には、大きな工場に、ブラジルやペルーから来て仕事をしていました。そのため、日系の方達はブラジルへ渡った1世から算えると、もう4世くらいの人が、日本に来ていることになります。近年は、愛知県などに工場が移動し、仕事が少なくなり、ブラジルに帰国する人も増えてきたようです。
では、テオさんの自己紹介から始めて、お話をお願いします。
グローバルセッション開始
テオさん:本日は参加していただきありがとうございます。私は、来日3年目になります。2022年に来日して京都民際日本語学校で1年間学び、就職し、正社員になりました。今は、その社員と翻訳者の二つを持っています。翻訳は主に、ゲームの翻訳でおもしろくて、楽しいです。Global Sessionのお知らせのタイトルから見てください。
タイトル:世界を繋げるには?
1.イントロダクション
架け橋>何をつなげる?
- 文化・社会・言葉・人・知識
2.翻訳者の仕事とは
- 技術的な面では?
- センスとしては?
- 探究心的面では?
愛国心的面では?
3.翻訳を味わいましょう
- 井関隆子日記 抜粋翻訳
4.翻訳の地獄と醍醐味
タイトルは、「世界を繋げるには?」ですが、何を繋げるのか?
日本人の常識は、「時間を守る」がありますが、ブラジル人は、守らないと言われています。遅刻することは、日本では許されないですが、ブラジルでは、ある程度はしてもよいと思われています。日本では当たり前の事が他の国では当たり前でないことがあります。そこに通訳が必要です。社会の常識などで、他の国の人には、理解できないこともあり、誰かが翻訳や通訳しなければ理解できないことが、実はたくさんあります。
Z・Yさん:日本人の友情と中国人の友情は同じと思いますか?どの面から見るかでちがいもあります。
テオさん:ことばの感覚のちがいもあります。ポルトガル語のサオタージュということばがありますが、普通は、恋しい、さみしいなどの意味ですが、お母さんの料理がなつかしいという場合にも使います。
M・Sさん:日本語で「おつかれさま、よろしくね」と言いますが、英語で最初に「おつかれさま」とは、言わないですね。
堤健介さんの登場(最後の参加者)
亀田さん:K・Tさん、自己紹介をまず、してください。
K・Tさん:亀岡に住んで、映画作りをし、脚本も書いています。(先月6月のゲスト)
テオさん:誰でも翻訳者になれるわけではありません。通訳は聴く力が必要で、翻訳は、読解力が必要です。また、母国語をしっかり理解している必要もあります。言語は生きているので、勉強は、一生しなければならないと思っています。言語はまた、時代を超えて行くので、新しい言い方も避けられないと思います。
センスとしては?
本音と建て前のちがい・ことばのあや・ジョークやだじゃれ・いやみや皮肉なども、文化を理解できなければ、いやみでもいいことを言っていると思い込むことがあります。
探究心的面では?
いろいろな人と関わる(経験は武器)
本をたくさん読む(語彙力を持たなければならない)
よく聴く・よく話す(あやしい人とも関わるとか・・)
愛国心的面では?
生まれ育った国が一番と思い、自国を知らないといけない。翻訳している相手はブラジル人なので。バランス感覚も必要
テオさん:ここまでで質問はありませんか?
Z・Yさん:「自国への愛が必要」と言われましたが、自国の良い所を言えても、悪いところをいうのは、ダメですか?
テオさん:愛国心は一番必要ですが、もちろん悪いところもありますが、自国が好きです。
E・Oさん:テオさんは、自国愛があるのですね。
テオさん:生まれた国が一番です。自分の国を出てきたのは、国がきらいというわけではなく、日本語が好きでもっとやりたかったからです。
児嶋:このメンバーの中には、仕事で外国に暮らした方達もいますよ。M・Sさんも日本人学校の教師として3年間シンガポールにいらしたし、私も家族でブラジルに3年間いました。
テオさん:「灯台もと暗し」という言い方がありますが、離れてから、よく見えて来ることがありますね。
3.翻訳を味わいましょう
テオさん:文化庁のコンクールの翻訳部門に挑戦しました。『井関隆子日記』という天保11年八月十六日の日付のある、文章で上巻と下巻の一部の文の日本語から英語への翻訳の課題です。みなさんにおくばりしますので、自分で現代語に一部でも翻訳してみてみださい。注釈もありましたが、完成するまでには16時間かかりました。

みなさんも翻訳してみてどうですか?難しいですね。翻訳された文を読んで見てください。
Y・Hさん:この時代に歯の治療をしてもらい、その後痛くて外したという話ですね。
グスタホさん:ポルトガル語で言ってもいいですか?
「・・・・・」
テオさん:翻訳をしているときには、となりの人に助けてもらいました。そうでなければ、もっと時間がかかっていたと思います。
Y・Hさん:この井関日記というのは、そうとう長いのですか?
テオさん:上巻と下巻の文章があり、課題が出ていました。
M・Sさん:外国人の方も多く挑戦されたのですか?
4.翻訳の地獄と醍醐味
テオさん:地獄というのは、孤独ですね。通訳の場合は、ひとりでやる仕事ではないのですが、疲れます。倒れた人は何人もいました。
亀田さん:長い時間はやれないですね。NHKなどでも通訳の人は、交替しながらやっていますね。
テオさん:翻訳者は、在宅勤務ですが、いろいろなことを調べなければならないので、地獄と醍醐味と両方あります。
M・Sさん:語彙力と語学力と両方必要ですね。2022年に来てから、日本語の学習を始めたのですか?
テオさん:日本に来る前の8年間ブラジルで、16歳から日本語学習をやっていました。日伯文化協会で。自分は日系ではありませんが、母は英語もやっていて、英語からポルトガル語に訳したり、その反対のポルトガル語から英語に訳して貰ったりしながら、学んでいました。技術翻訳は、難しくはないけれど、おもしろくなかったです。
Y・Hさん:16歳で日本語を始めたと言われましたが、その動機はなんだったのですか?
テオさん:母が日系の方達と関わりがあり、「おばあちゃん」と呼んでいた人とも親しくしていました。その方は、100歳で亡くなりました。
おじいちゃんの親友に堀ジューンさんという人がいて、漫画やアニメなどの日本語をポルトガル語にして見せてくれました。なんだかパズルを解くような感じで、自分の手でやってみたくなりました。
今日の資料は、児嶋さんから、またメールで送ってもらうようにします。
M・Sさん:AIがやる時代が通訳、翻訳の世界にも来るかもしれませんね。テオさんは、どう思いますか?
テオさん:確かに話題になっていますね。AIは業界を変えるのではないかと。
M・Sさん:競争相手がAIとか。
テオさん:情報だけ伝えることはできると思います。ただ、クリエーティブにことばを替えながらやることはAIではできないと思います。最低レベルで理解したことの翻訳などは質は悪くないと思います。
M・Sさん:翻訳ではAIの力は疑問がありますね。ロンドンで吉本ばななさんの小説の翻訳がとても売れているようですが、翻訳者が育っているのですね。作者の個性を、日本語から英訳することでも出せているのですね。
テオさん:今回の文化庁のコンクールを出版するのは、コンクールの翻訳者で、出された物は、皆ちがうはずですね。でも、AI翻訳なら、ひとつでコピーになりますね。
グスタホさん:人はみなちがうので、翻訳もちがうでしょう。
Y・Hさん:文学作品は、ちがうはずですね。文化に根ざしていますから。AIがすべて組み取ことはむずかしいでしょう。
児嶋:文学作品の翻訳を読むことも、その国の言葉を理解する上で大切なことだと思います。
私は、今ハングルをラジオ講座などでも学んでいますが、その国を理解することが。言葉の理解にもつながるので、最近は、ハングル文学などを日本語に翻訳され出版された本を何冊も読んでいます。語学の奥の理解ができるようで。
テオさん:AIが使う能力は、完璧ではないです。AIに丸投げしてはよくないですね。翻訳者としては、自分の長所は、クリエーティブでおもしろい文が書けることと思いますが、弱点は、文法力が低いので、ときどきAIに聞くことがあります。
K・Tさん:『井関隆子日記』を翻訳されて難しかったことはありますか?
テオさん:上巻の最後に短歌がありますね。
「もえ出る春ともいはずかなしきは老その森のおちばなりけり」
注釈:もえ出(いず)る春:歯が抜けたのが「如月(きさらぎ)のころ」
如月(二月)は盛春なので、このように詠みだした。
テオさん:如月は初春なので、盛春とはいいにくいのではないか?
「歯の落ちる」と「葉の落ちる」をかけているが、翻訳で英語にしたら
どこまでニュアンスを近づけていけば良いか
E・Oさん:思考がおいつかないのですが、現代日本語を英語やポルトガル語には翻訳できる人も多いと思いますが、古代語を英語に直すなんてテオさんは、すごいですね。
テオさん:自分の文化は、誰でも少しはわかると思いますが、翻訳者になりたい人は、たくさん本を読むといいと思います。
E・Oさん:テオさんは大学時代から、翻訳もやっていたのですか?
テオさん:大学時代は、通訳や翻訳はしませんでした。
児嶋:私が英語で通訳や翻訳をしなければならなかったのは、亀岡にオクラホマ州立大学京都校が1990年に開校してからです。それ以前から、開校準備で英語でのやりとりをしていましたが、その学校にやってきたアメリカ人の教授たちは、日本語は話せないので通訳もし、日本人のスタッフも話せる人は小数だったので、相互のコミュニケーションのために朝から晩までやっていたのが初めてでした。でも、自分が話したり、書いたりするのは楽ですが、他の人のために通訳、翻訳するのは、だんだんむかついてくることもありました。
亀田さん:私は、観光ガイドの仕事ですが、通訳はしんどいです。言われた事を通訳しなければならないし、それも正確にです。自分のイメージで話してしまうこともよくあります。
テオさん:私も先に通訳をしていたのですが、翻訳者に切り替えました。
亀田さん:今日の内容も大変ですが、その時代によって状況もちがうので、わかりやすくするために、日本の天保年間は、たとえば、英国では、いつごろかなどの説明もいるのではないでしょうか?
では、12:30も過ぎましたので、これで、おわりにしましょう。