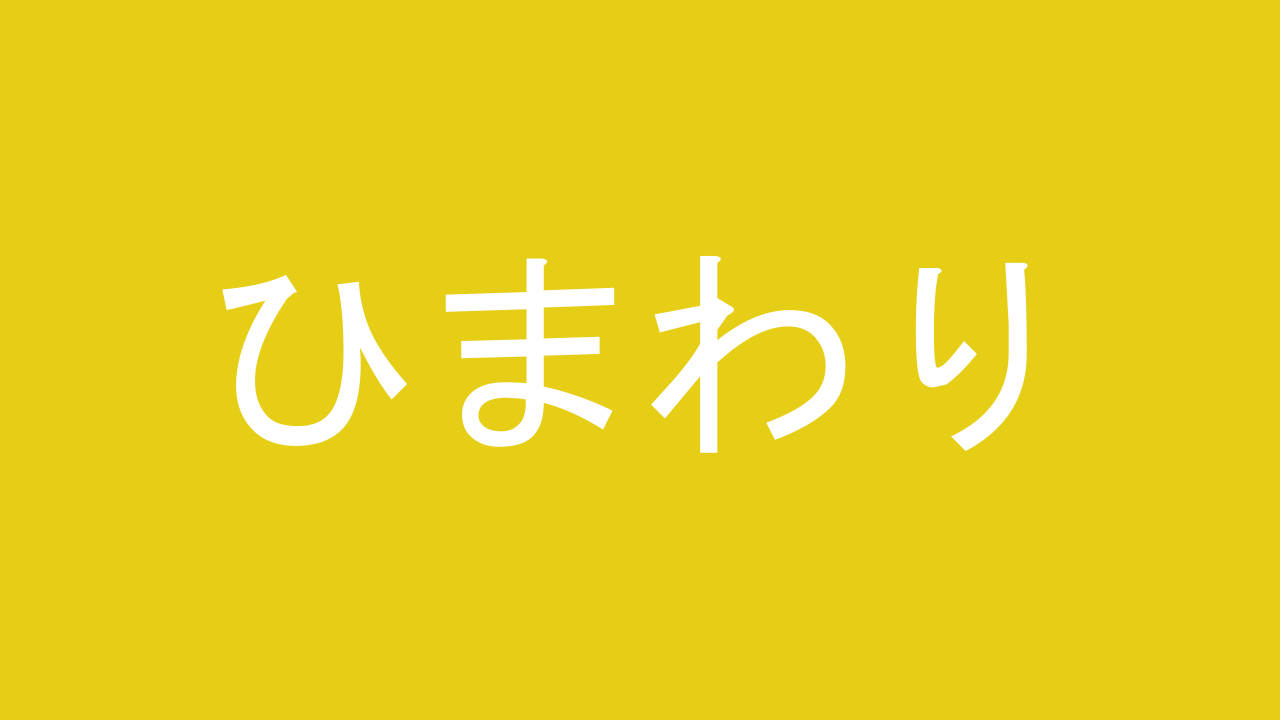ひまわり教室について
ひまわり教室では、外国につながる子供の学校での学習に必要な語学力の学習支援と、その保護者の日本語学習支援を行っています。
子どもと保護者が同じ教室内で同じ時間帯にそれぞれの学習を行っています。
指導者は、元教師など多くは子どもへの学習支援経験者です。
亀岡市内をはじめお隣の南丹市からも子どもたちが通っています。
ひまわり教室日記
-
2024/02/22 報告
外国につながる子ども・保護者のための居場所つくりを考える研修会(2023年度第2回目)レポート
開催日時:2024年2月10日 午後1:30~3:30 場所:ガレリア2階 大広間 講師:エニ・レスタリさん(インドネシア出身・大学講師・京都市在住) タイトル:他国「日本」でのストーリーとコミュニティとのつながり 司会&コーディネーター:児嶋きよみ 参加者:15名 亀岡市国際交流協会&オフィス・コン・ジュント共催 プログラム エニ・レスタリさん当日資料 私は1996年に日本人と結婚して、200
…続きを読む -
2023/11/13 報告
2023年度ひまわり教室関連活動実施状況(11月現在)
2023年11月の現在のひまわり教室関連の活動実施状況です。 4月:ひまわり教室 2回開催:4月2日(日)、4月16日(日) 4月13日 小学校校長会へ参加し、ひまわり教室について説明 4月21日 中学校校長会へ参加し、ひまわり教室について説明 5月:ひまわり教室 2回開催:5月7日(日)同上、5月21日(日) 5月30日:宇治市で児嶋がひまわり教室について発表 6月:ひまわり教室 2回開催:6月
…続きを読む -
2023/02/03 報告
外国につながる子ども・保護者のための居場所つくりを考える研修会レポート
2023年1月28日(土)13:30~16:00 ガレリアかめおかの2階大広間にて、2022年度第2回研修会を開催しました。 亀岡市国際交流協会&オフィス・コン・ジュント共催です。 「公立中学校の国際教室で行う母語を活用した教科学習支援の実際~ 誰が・どのような支援を・どのように行っているのか~ 」というテーマで開催しました。 講師は、清田淳子さん(立命館大学文学部教授)と王植さん(オンラインでの
…続きを読む -
2022/08/17 報告
2022年7月17日(日)外国につながりをもつ子どもの学びを支える研修会
開催:2022年7月17日(日) 10:15~12:15 場所:ガレリアかめおか 2階大広間 講師:大野友アンドレイアさん(箕面市国際交流協会職員)ブラジルから14才で来日。現在は箕面市国際交流協会の職員として外国ルーツの子どもをサポートする活動を行っている。 内容:1.講座「マイノリティと日本社会の狭間で」(10:20~11:10) 2.セッション(質疑応答)(11:10~12:15) 参
…続きを読む -
2022/04/07 報告
2021年度ひまわり教室関連の報告
2021年4月から2022年3月までのひまわり教室に関連する1年間の報告です。 2021年度のひまわり教室 2021年度、ひまわり教室は、二教室で開催してきました。 馬路教室は、亀岡市馬路文化センターで火曜日の午後6:00~8:00で開催 中矢田教室は、大本愛善苑会館で木曜日の午後6:00~8:00で開催 子どもの参加費:300円、保護者参加費:無料でした。 ※8月からはコロナ禍のため、おもにガレ
…続きを読む -
2021/12/01 ひまわり教室について
「共に生きる」ために 2021年11月28日京都新聞掲載
遠くにいても話し合いができる環境が整ってきていると感じる機会が増えていたのがコロナ禍のひとつの成果でしょうか? 2014年に外国につながる子どもさんとお父さんやお母さんの学習支援のひまわり教室を開設し、2021年現在も、細く長く続けています。 同時に、指導者が学び会う研修会も毎年京都府国際センターや亀岡市の国際交流協会の共催でやっています。 今回は、「国際教室」を小学校で340校の内147校(43
…続きを読む -
2021/05/14 ひまわり教室について
2021年度のひまわり教室について
2014年に2人の外国出身のお母さんから子どもの「勉強を見てほしい」と言われたのが、ひまわり教室が始まるきっかけでした。 コロナ禍で制限もありまますが、2021年度も引き続きひまわり教室を開催していきます。 2021年度の教室の内容と特徴 1.多言語での読み聞かせ(保護者の母語に子ども達が関心を持つように)(馬路教室) *中国語・英語(フィリピン出身の母親)・スペイン語(メキシコ出身)と日本語で読
…続きを読む -
2021/05/13 ひまわり教室について
ひまわり教室から皆様へ
子どもは言葉の天才だと言われています。特に外国語の習得は大人より驚くほど早いという話は1度ぐらいお聞きになったことがあるではないでしょうか。でも、実は子どもにとっては、外国で<その国の言葉で生活することと<その国の言葉で勉強することは全く違うことなのです。なぜなら、使われる言語能力が違うからです。 バイリンガルの子どもの言語能力は、「生活言語能力」(BICS*)と「学習言語能力」(CALP**)を
…続きを読む -
2021/05/13 報告
2020年度の指導者meeting及び研修会
指導者meeting2020年7月23日(木・祝)10:30~12:00 ガレリア3階会議室ゲスト:堀江亜希子さん(京都府国際センター)京都府国際センターの「外国につながる子ども」に関わる事業について 支援者研修会meeting2021年1月30日(土)1:30~3:30 (オンラインで30名以内)(オフィス・コン・ジュント・京都府国際センター&亀岡国際交流協会共催)・児嶋きよみ(外国につながる子
…続きを読む -
2020/03/21 報告
2019年度ひまわり教室に関する発表一覧
6月7日(金)17:30~ 京都教育大学浜田麻里教授主催学習会にて、ひまわり教室巣の絵本作りについて発表。発表者:滑川恵理子 サポート:児嶋・末永 8月7日(水)、8日(木) 立命館大学衣笠キャンパスMHB研究大会(母語「・継承語・バイリンガル教育学会)ポスターセッション:児嶋きよみ 「ひまわり教室について」 8月20日(火)13:30~16:22 キャンパスプラザJIAM(全国市町村国際文化研修
…続きを読む